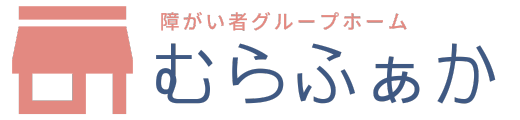2.1. 業務効率化で「本来の支援」に集中できる
ペーパーレス化による最も直接的な効果は、業務の劇的な効率化です。
- 情報共有の迅速化 : 記録した情報はリアルタイムで全職員に共有され、申し送りがスムーズになります
- 記録作業の負担軽減 : 一度入力したデータは様々な帳票に反映でき、何度も同じ内容を書く手間がなくなります
- 保管スペースの削減 : 大量のファイルが不要になり、事業所のスペースを有効活用できます
ただし重要なのは、効率化で生まれた時間は目的ではなく、「より質の高い支援」を実現するための貴重な資源だということです。
2.2. データ活用で支援の質が向上する
Before: 紙ベースでの手作業
3週間
(21日間)
After: 電子化 + AI分析
3日
(作業効率が劇的に改善)
電子化は単なる効率化ツールではありません。蓄積されたデータを活用することで、支援の質そのものを大きく向上させることができます。
AIによるアセスメント、個別支援計画の原案作成。「むらふぁか」では、日々の支援記録データをAIに読み込ませ、利用者さん一人ひとりの特性や過去の支援経過に基づいたアセスメント、個別支援計画の原案を自動作成する仕組みを構築しました。AIは人間では見落としがちな行動パターンや変化の兆候を客観的に抽出し、要約やアドバイスを提示してくれます。3週間かかっていた作成時間が3日で終わるという劇的な変化です。
ご家族とのリアルタイムな連携強化。利用者さんの日々の支援記録をご家族に毎日共有することで、「昨日はこんな様子だったのですね」「この支援について、家庭ではこうしていました」といった反応やアドバイスがすぐに得られます。事業所と家庭が一体となった、より質の高い支援が実現できています。また、ご家族からの感謝の言葉が支援者に直接届くことで、職員のモチベーション向上にもつながっています。
2.3. 若手職員が定着する「働きやすい環境」を実現
障害福祉の現場では、人材の確保と定着が大きな課題です。デジタルツールを使いこなすことが当たり前の若い世代にとって、ペーパーレス化は「働きやすい」と感じられる環境を作る重要な要素です。
むらふぁかでは支援記録にGoogleスプレッドシートを利用しています。インターネット環境さえあれば場所を選ばず記録の確認や記入が可能です。これにより事務作業のための残業を減らし、柔軟な働き方が可能になります。結果として優秀な人材の確保と定着に大きく貢献しています。